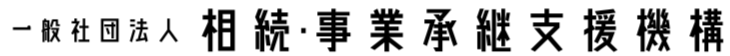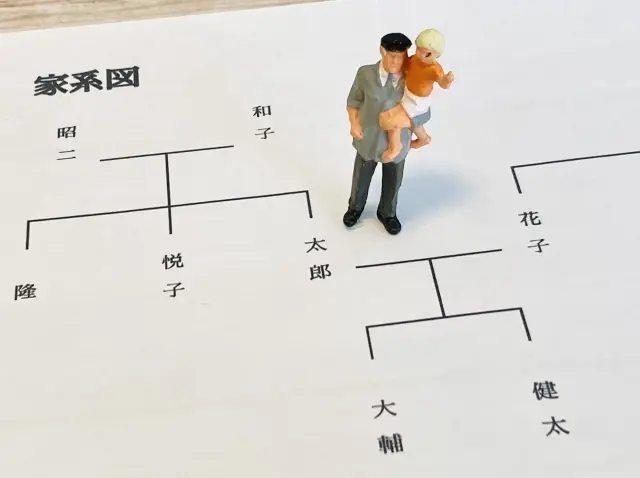~判断能力が低下したあとに、家庭裁判所が選ぶ支援者~
目次
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方(認知症・知的障がい・精神障がいなど)に対し、家庭裁判所が後見人を選任し、本人を支援する制度です。
本人の利益を最優先に、生活や財産管理、契約行為などをサポートします。
法定後見人の役割
法定後見人は、本人の代わりに以下のようなことを行います。
- 預貯金や年金の管理
- 介護・医療・施設との契約や手続き
- 不動産の売却や賃貸契約
- 悪質商法などから本人を守る
法定後見の種類(3つの類型)
本人の判断能力の程度に応じて、法定後見には以下の3種類があります。
| 種類 | 対象となる方 | 支援の内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない方 | 全般的に代理・取消が可能 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な行為に同意・代理 |
| 補助 | 判断能力が一部不十分な方 | 必要な範囲で同意・代理 |
法定後見人は誰がなるの?
後見人は、家庭裁判所が選任します。親族が選ばれることもありますが、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースも増えています。
本人の利益を守るため、中立性や専門性が重視されます。
任意後見との違い
| 比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力が低下したあと | 判断能力があるうちに契約 |
| 後見人の選定 | 家庭裁判所が決定 | 本人が自由に選べる |
| 契約の有無 | 契約なし(申立てによる) | 公正証書による契約が必要 |
法定後見制度の流れ
- 医師による診断書の取得
- 家庭裁判所へ申立て(親族・市区町村長など)
- 調査官の面談や審理
- 審判により後見人の選任・開始
費用について
法定後見制度の利用には、以下のような費用がかかる場合があります。
- 申立費用(印紙・郵便代・鑑定費用など)
- 後見人報酬(家庭裁判所が決定)
※生活保護世帯や低所得の方については、報酬付与が免除されることもあります。
当サイトでできること
- 法定後見の申立てサポート
書類準備・家庭裁判所への申立て手続きなど、全面的に支援いたします。 - 親族が後見人になる場合のアドバイス
責任や業務内容をしっかりご説明し、不安を解消します。 - 専門職後見人のご紹介
中立的な専門家による後見をご希望の場合にも対応可能です。
ご本人とご家族を守る、大切な制度です
法定後見制度は、判断能力が失われたあとでも、安心して生活を続けられるための「法のセーフティネット」です。
ご家族の負担を減らし、大切な財産と権利を守るために、ぜひ正しい知識を持ってご検討ください。
📞 ご相談受付中: 無料で相談する